こんにちは。Tomoyuki(@tomoyuki65)です。
SRE(Site Reliability Engineering)について学びたいと思い、2025年11月時点での最新の本として「SREの知識地図——基礎知識から現場での実践まで」を購入して読みました。
SREについては実サービスを中長期的かつ安定的に運用していくために重要だと思うので、この本で学んだ基礎的なことや大事なポイントについてまとめておきます。
SRE(Site Reliability Engineering)の基礎と大事なポイントまとめ
SRE(Site Reliability Engineering)とは?
SRE(Site Reliability Engineering)は日本語にすると「サイト信頼性エンジニアリング」のことで、具体的には「サービスを止まらずに安定して動かすために、運用をエンジニアリングで効率化・自動化する仕事や考え方」 のことを指します。
そんなSREというのは、サービスを成長させながら、信頼性を保ち続けるための仕組みづくりを担っており、スピードと安定性の両立が求められる今の開発現場では欠かせない役割になっています。
SLO(Service Level Objective)の定義と運用が大事
SREではまずサービス毎に適切なSLO(Service Level Objective)と呼ばれるサービスの信頼性に関する「目標値」を明確に定めることが出発点です。
※SLOの例:「月間の稼働率を 99.9% にする」など
次にSLOに対して実際の運用結果を常に監視(モニタリングツールを適切に利用)し、監視の結果から「SLOを達成できている/できていない」を判断します。
※ただし、SLOをリアルタイムで完璧に追いかけるよりも傾向を把握し改善に繋げることが重要なので注意。
その際にSLO違反があった場合は、どの改善が優先かを判断することができるため、開発リソースの優先度をユーザー体験と信頼性に直結させることが可能です。
このように、「SLOを定義 → モニタリング → 結果をもとに優先度を決めて改善」を繰り返すことがSREの基本であり、それが無駄な運用作業を減らし、サービスの信頼性を体系的に改善することに繋がります。
関連記事

障害発生時には「ポストモーテム」による学びが大事
実サービスにおいては必ず何らかの障害が発生するものだと思いますが、その際はポストモーテム(システム障害や重大なインシデント発生時、その原因や影響、対応プロセスを振り返り、学びを得るために行う分析プロセス)と呼ばれる事後分析をしっかり行い、同じ問題を繰り返さないようにするためにチームの学びとして活かしていくのが大事です。
特に誰かが原因で発生するようなインシデントなどにおいては、その人を責めることはせず、サービスを安全に運用させるための学習プロセス(障害から学ぶ仕組み)であることがSLOを守り続ける上で非常に重要です。
障害対応に向けたオンコール体制はしっかり整えるのが大事
実サービスにおいて、障害が起きてもそのサービスを守れる仕組みを作るためには、オンコール体制(障害発生時に即座に対応できる人や仕組みをあらかじめ決めておく体制)をしっかり整えるのが大事です。
ただし、オンコール体制のための担当者には時間的負担、心理的負担、そして生活への影響などもあったりするため、コストがかかってもしっかりとした体制を整えることは必須です。
トイルは全体の50%以下に削減する
実サービスの運用においてはトイル(反復的で自動化できる運用作業のこと)が多々発生することになったりするが、トイルが多いとエンジニアが価値のある改善や開発に使える時間が減るため、全体の50%以下になるよう常に削減していくのは大事です。
必要に応じてPRR(Production Readiness Review)を実施する
重要な変更を本番環境にリリースする際は、必要に応じて(リスクや影響度に応じて)PRR(Production Readiness Review)を実施するのが大事です。
※PRRはチェックリストを用いて、新しいサービスや機能が本番環境で安全に稼働できるかを事前に確認するプロセスです。厳密なレビューをすればするほどリリースのスピードが落ちるのでその点は注意が必要です。
SREの組織作りについて
SREの組織作りには「これが正解」という形があるわけではないため、プロダクトの性質や組織の成熟度に合わせて柔軟に設計することが重要になります。
特にSREチームを作るというのは、サービスの信頼性と開発スピードのバランスを最適化することにあるため、「自社のプロダクトフェーズ × 組織の文化 × 技術的成熟度」によって柔軟に設計することが成功の鍵になります。
最後に
今回はSREの基礎と大事なポイントをまとめました。
より詳しい内容を知りたいという方は、ぜひSREに関する本「SREの知識地図——基礎知識から現場での実践まで」を購入して読んでいただければと思いますが、大事なポイントはまとめておいたので、振り返りたい方はぜひ参考にしてみて下さい。

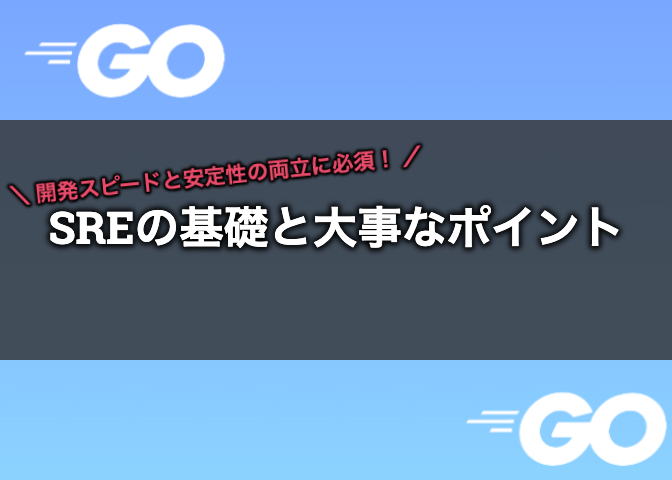
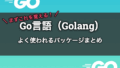
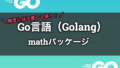
コメント