こんにちは。Tomoyuki(@tomoyuki65)です。
Goエンジニアの仕事というのは主にバックエンドエンジニア領域の仕事になると思いますが、個人だったり、小さい組織や小さいプロジェクトになればなるほど、バックエンドエンジニアがインフラ領域の仕事も兼ねるということが多いと思います。
そのため、Goエンジニアを極めていくというのはつまり、インフラ面の知識やスキルも磨いていく必要があります。
私も専門性としては主にバックエンドのスペシャリスト方面を主軸にしていますが、これまでもコツコツとインフラ面の勉強をしてきました。
ということでこの記事では、私が取り組んできたインフラに関する勉強についてまとめておきますので、興味がある方は参考にしてみて下さい。
Goエンジニアにおけるインフラの勉強について
AWSやGoogle Cloudなどのクラウドインフラを使って試してみる
現在のWebサービス開発においては、AWSやGoogle Cloudなどのクラウドインフラを用いてインフラ環境を構築するのが一般的ですが、それらの知識やスキルを得たいならまずは実際に触ってみるのが大事です。
基本的な使い方については検索すればブログなどでたくさんの情報が公開されているので、それらを参考にするといいでしょう。(情報が古くなっていることも多いのでその点は注意)
注意点としては、クラウドインフラは基本的には従量課金であり、アカウント登録にはクレジットカードが必要になったりしますが、アカウント登録ができれば個人での利用も可能です。
特に新規アカウント作成時は数ヶ月間いくつかのサービスが一定量無料で使えたりするので、そういうのも駆使してできるだけ無料で試せるといいと思います。
関連記事
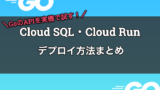

CI/CDを試す
アプリケーション領域にも関わっていて、インフラ面で大事なこととしては、CI/CDになると思います。
※CI/CDはContinuous Integration(継続的インテグレーション)/Continuous Delivery(継続的デリバリー)の略です。
これはソフトウェア開発におけるコード変更時におけるテストの自動化や、各種環境にデプロイさせる部分の自動化をすることを指します。
最近はコード管理用のプラットフォームであるGitHubと合わせて、GitHub Actionsを用いてCI/CDを構築することも多いと思うので、試そうと思えば簡単に試せると思います。
実務でもAWSやGoogle Cloudなどのクラウドインフラを使う
実際に仕事をしている方であれば、実務においてAWSやGoogle Cloudなどのクラウドインフラを触る機会がある人もいると思います。
クラウドインフラは従量課金であり、個人で学ぶにはどうしても限界があったりするので、実際に実務でクラウドインフラを触る機会があった場合はとても大きな経験を得られると思います。
AWSかGoogle Cloudのどっちを学べがいいかについて
主要なクラウドインフラとしてはだいたいAWSかGoogle Cloudになると思いますが、どちらを学べばいいか迷う人もいると思います。
日本における実務でよく使われているのはだいたいAWSになるので、特に理由がなければまずはAWSを学ぶことをおすすめします。(AWSの方が仕事を得やすいため)
※AWSならEC2、ECR、ECS、App Runner、Apmlify、RDS、ElastiCache、Lambda、S3などで必要そうなやつを学んでおくといいです。
ただし、個人や小さい組織、小さいプロジェクトの場合や、UI/UXが使いやすい方がいいという場合においてはGoogle Cloudの方が優れているので、そういう場合はGoogle Cloudを学んでもいいと思います。
Google Cloudに関する本を読む
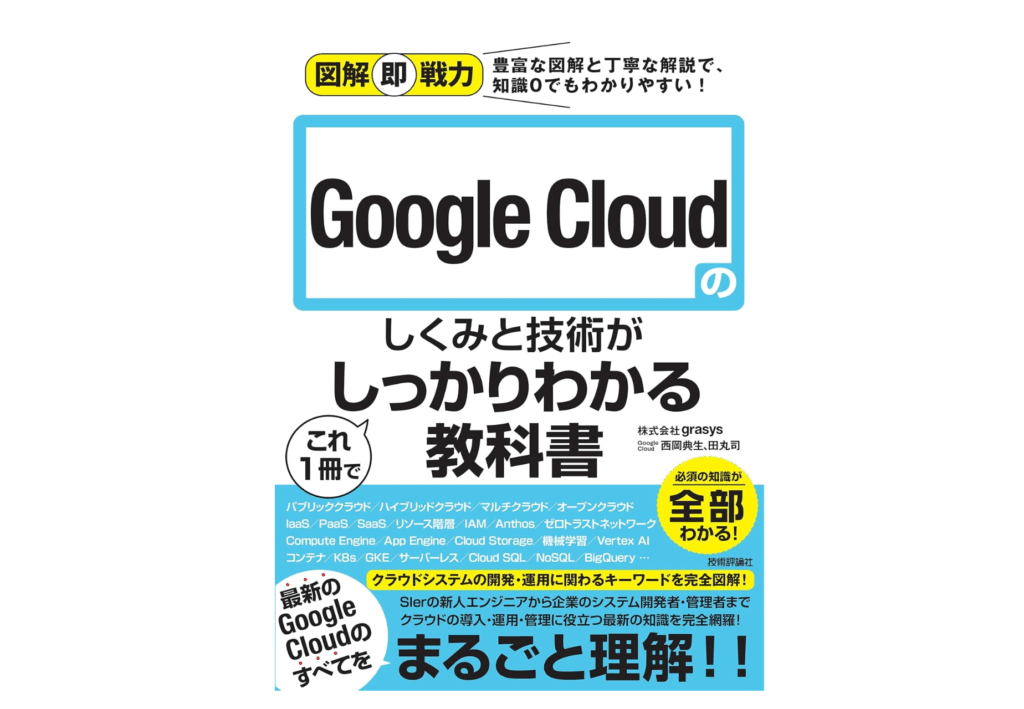
私としてはGo言語がGoogle製ということもあって、Google Cloudを極めたいなと思ったので、Google Cloudに関する本として「図解即戦力 Google Cloudのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書」を購入して読みました。
この本に関しては全てをしっかり読むというよりかは、知りたいサービスがあった時にサラッと読んで知見を深める感じに利用しています。
Google Cloud Associate Cloud Engineerに関する本を読む
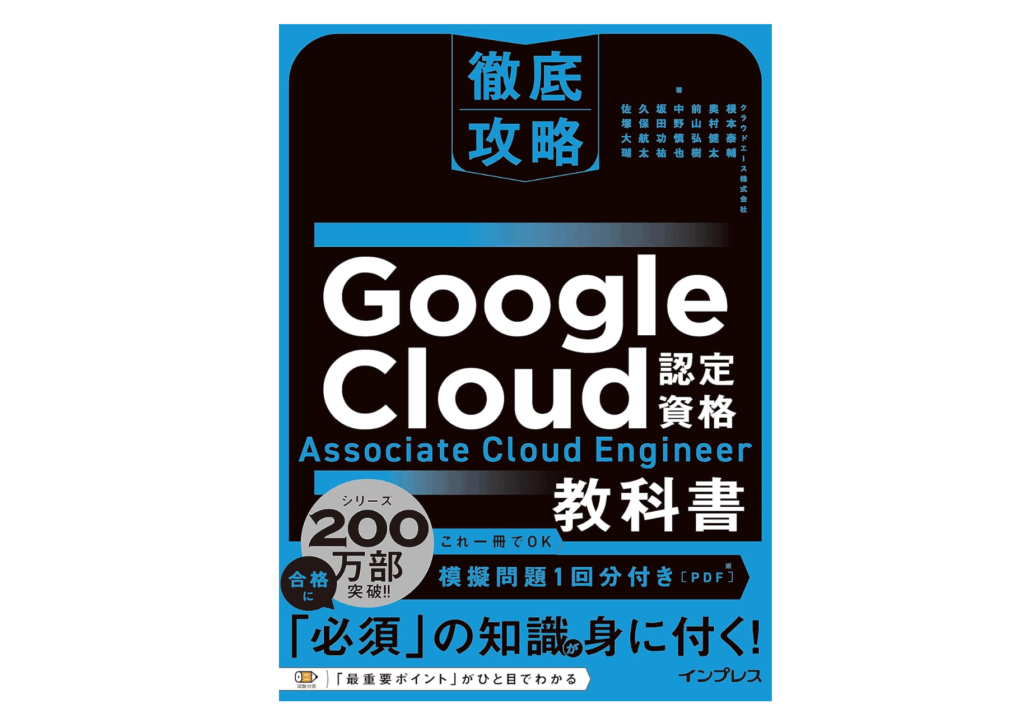
クラウドインフラの知識やスキルがあることを可視化するための簡単な方法としては、各種クラウドインフラにある資格を取得することです。(もちろん資格取得を目的とはしません)
最終的には上位の資格を取る前提ですが、まずは下位の資格に関する勉強から始めるべきかなと思い、Google Cloud Associate Cloud Engineerに関する本「(模擬問題付き)徹底攻略 Google Cloud認定資格 Associate Cloud Engineer教科書」を購入して読みました。
この本に関してはこれからGoogle Cloudの資格を取得するための土台になってくるため、ある程度しっかり読んで学ぶことを意識しました。
とはいえ、あまり深く読みすぎても効率が悪いので、この本で学ぶことにはあまり時間をかけすぎないようにしています。
IaCツール「Terraform」の使い方を学ぶ
最近だとインフラ環境はIaCツールを用いてコード化してGitHubなどで管理することが多いので、そんなIaCツールとしてよく使われている「Terraform」についての使い方を知っておくのは大事です。
※IaCとはInfrastructure as Codeの略で、インフラをコード化することです。
関連記事
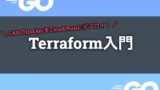
SREに関する本を読む
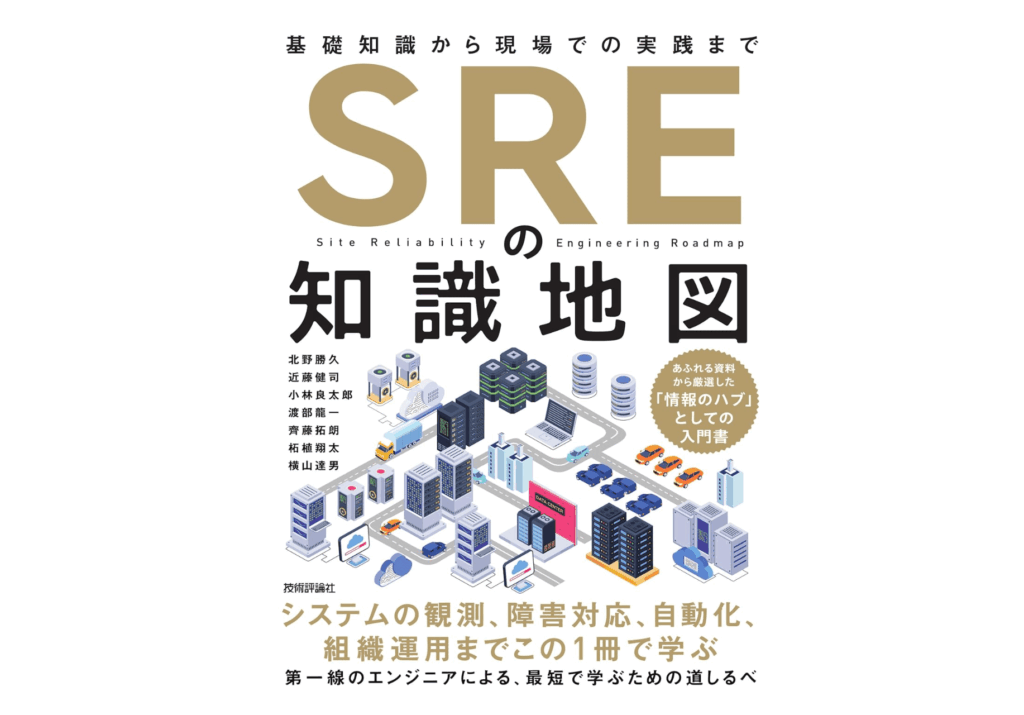
組織やプロジェクトの規模、そしてプロダクトの状態にもよりますが、ちゃんとしたサービスを中長期で安定的に運用していくなら、SER(Site Reliability Engineering)に関する知識も大事になります。
※SREとはソフトウェア開発と運用の両方の知識を活用し、サービスの信頼性を向上させるための手法のことです。
どちらかというとインフラエンジニア領域ではあるため、バックエンドエンジニア視点では馴染みが薄いものだと思いますが、特に小さい組織やプロジェクトならバックエンドエンジニアがインフラ領域も兼ねることがあるため、そういった時にSERについての知見があると活きると思います。
2025年11月時点での最新の本として「SREの知識地図——基礎知識から現場での実践まで」が発売されていたので、これを買って読みました。
この本に関してはSREってどういうものかが全体的にまとまっていて、SREについて知りたいと思っている人が最初に読む本としては最適だなと思ったのでおすすめです!
関連記事

Professional Cloud DevOps Engineerの資格取得に向けた勉強
私の現時点でのインフラ面に関する最終目標としては、Google Cloudの「Professional Cloud DevOps Engineer」の資格を取得することなので、次はこれについて学んでいく予定です。
これを学ぶのによさそうな日本語の本は無いので、Google公式のGoogle Skillsにある「DevOpsエンジニア学習プログラム」というので学んでいくことになりそうです。
実際にやってみないとどうなるかはわかりませんが、ちょっと試しにやってみたいと思っているので、また何か情報があれば後日追記します。
最後に
今回は私が取り組んできたインフラに関する勉強についてまとめました。
Goエンジニアとして極めていくためにもインフラの知識やスキルは確実に必要になるため、バックエンドエンジニアの道を歩んでいる方もコツコツ勉強していくのが大事になります。
もしインフラに関してはこれから勉強するという方がいたら、ぜひ参考にしてみて下さい。

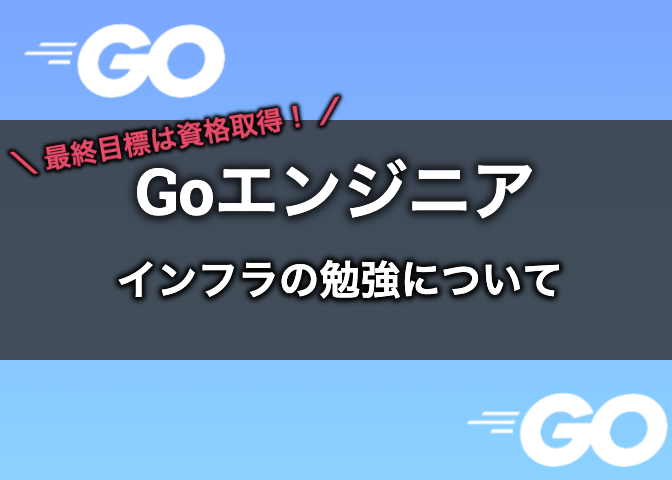
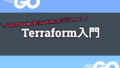
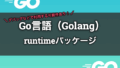
コメント